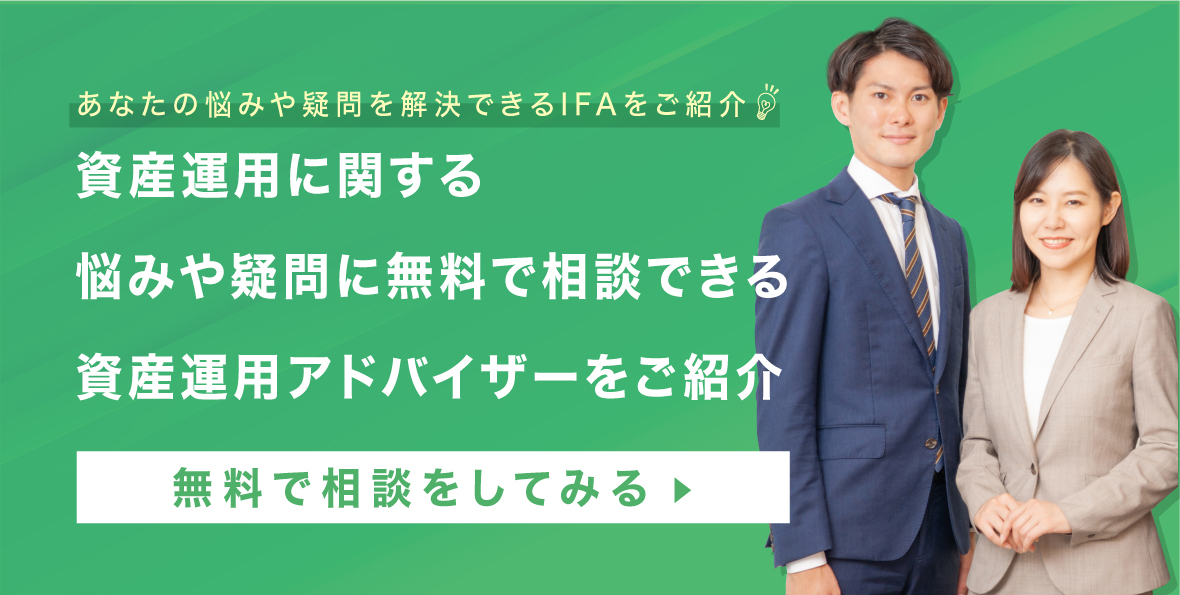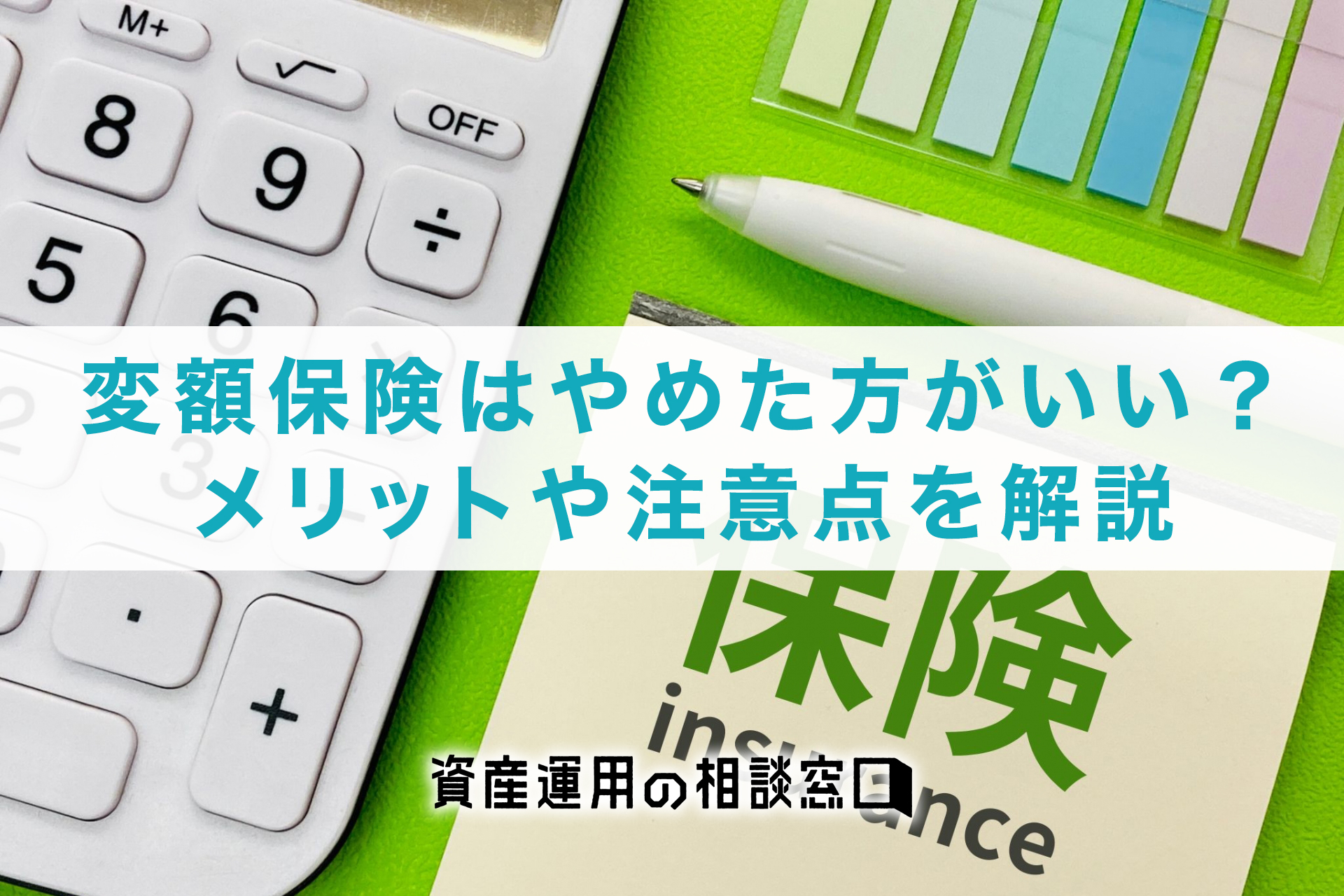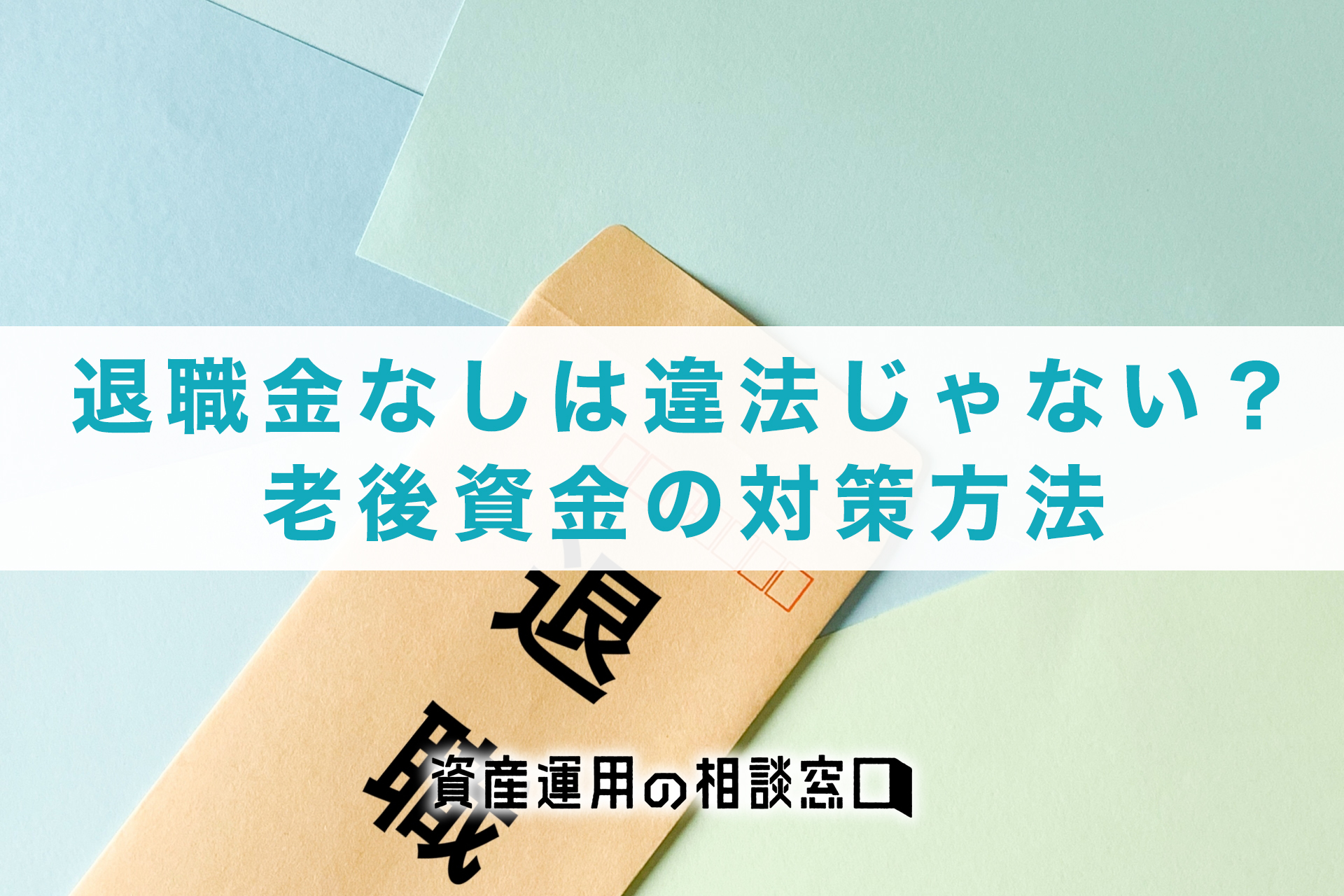「退職金の運用方法がわからない」「自分に合った投資商品が知りたい」など、退職金の運用方法について疑問を持っている方もいるでしょう。運用方法によって特性やリスクが異なるため、自分に適した選択肢を見つけることが大切です。
本記事では、退職金のおすすめ運用方法ランキングについて紹介します。さらに、退職金を安全に運用するための注意点や、おすすめの相談先についても解説しています。
退職金の運用を検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください。 
退職金を運用した方がいい理由とは?
退職金を運用した方がいい理由は、老後2000万円問題や公的年金だけでは生活費が足りない可能性があるためです。また、インフレによって資産の価値が低下するリスクもあります。
かつては、退職金があれば老後も安泰とされていましたが、現在では退職金が減少している会社もあり、中には退職金がない会社もあります。
厚生労働省(中央労働委員会)の「令和3年賃金事情等総合調査」によれば、大卒の退職金の平均額は以下のとおりです。
・勤続35年:1,903万3,000円(2,157万8,000円)
・満勤勤続:2,230万4,000円(2,289万5,000円)
※()内は令和元年調査時
老後の生活費を確保するには、退職金に加えて十分な貯蓄や収入が必要です。
ここでは、退職金を運用した方がいい理由について詳しく見ていきましょう。 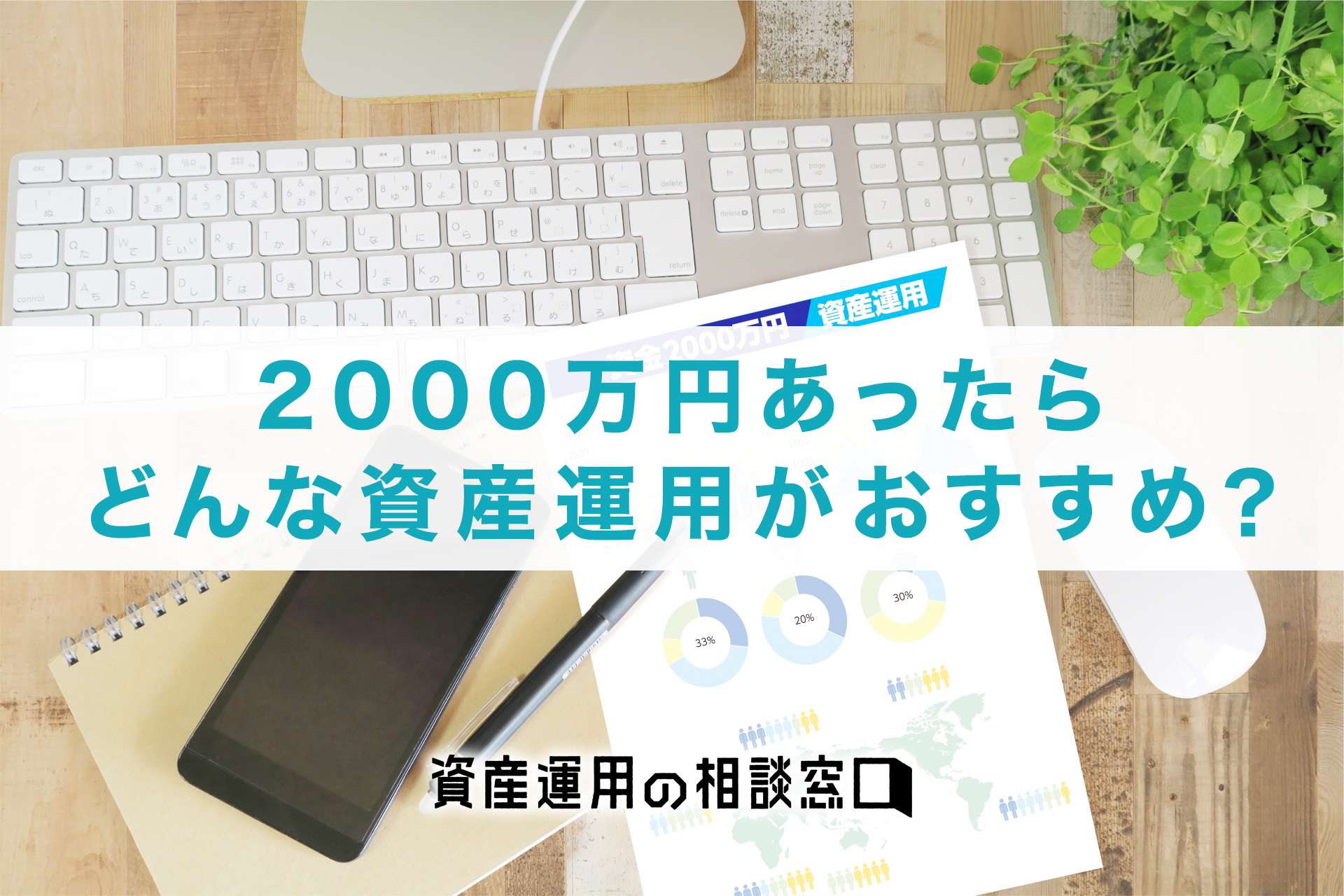
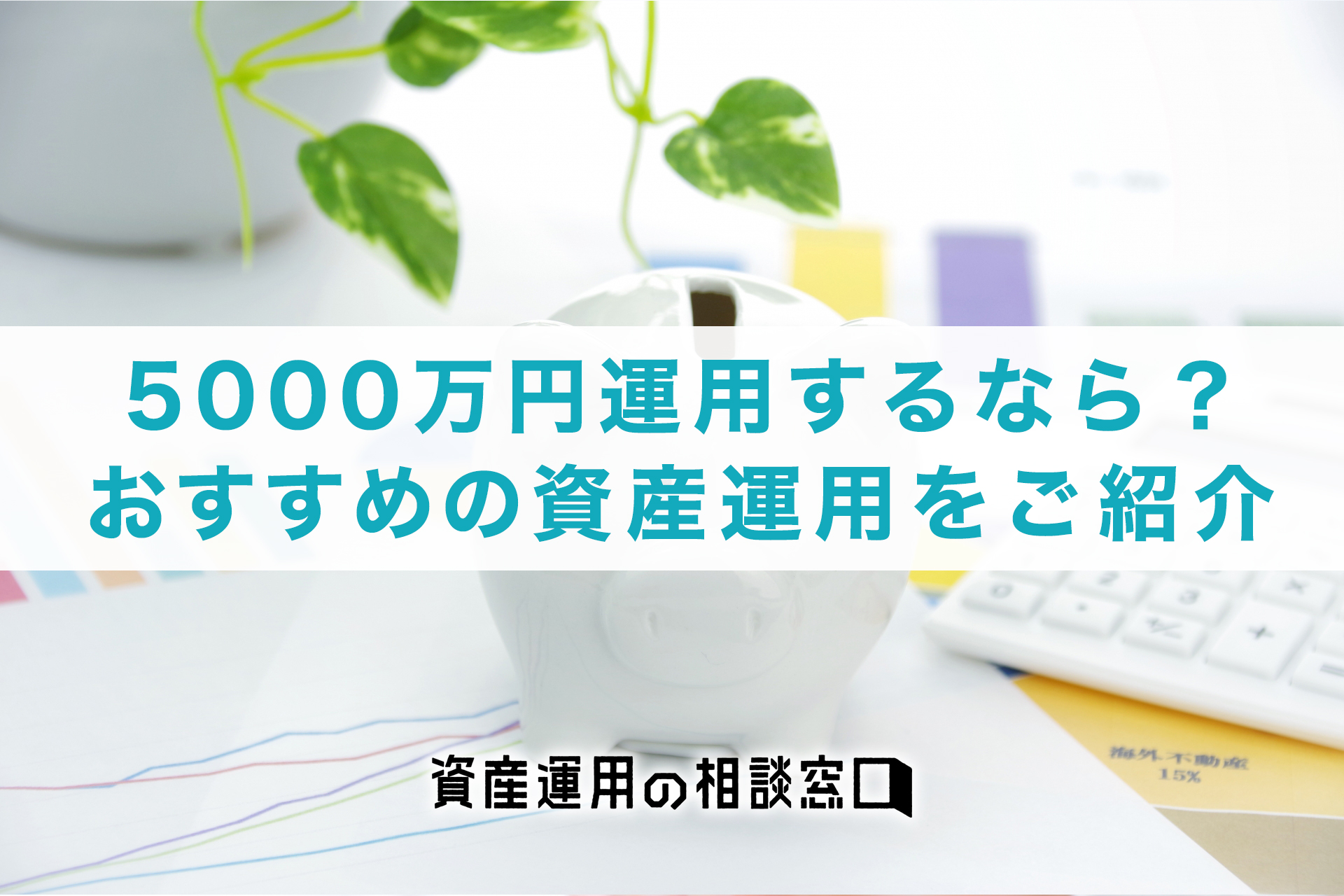
平均寿命が伸びている(定年退職後の人生は長い)
退職金を運用した方がいい理由の一つが、平均寿命が伸びているからです。
厚生労働省の「令和4年簡易生命表の概況」によると、男性の平均寿命は81.05歳、女性の平均寿命は87.09歳です。
過去と比べて平均寿命が大幅に伸びています。
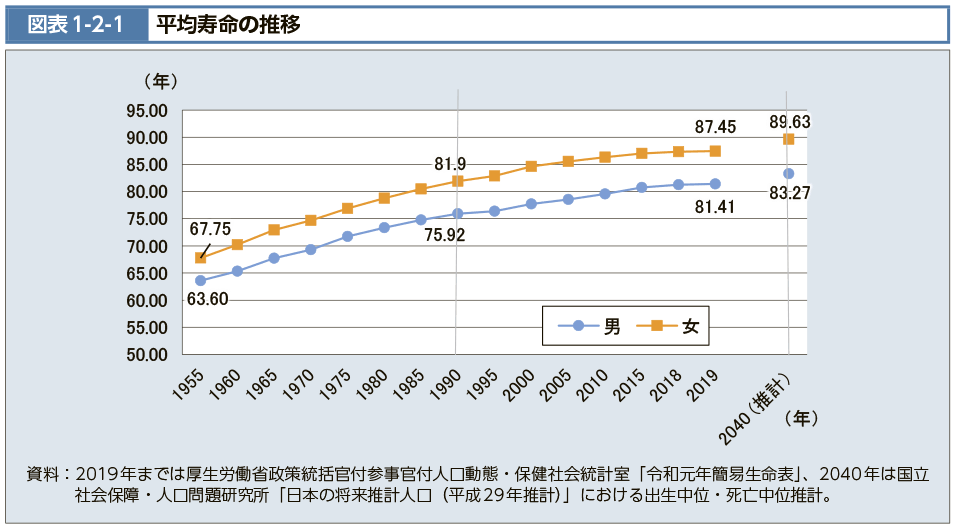
引用:厚生労働省「平均寿命の推移」
・1955年:男性63.60歳 女性67.75歳
・1990年:男性75.92歳 女性81.90歳
・2019年:男性81.41歳 女性87.45歳
定年が65歳の場合、現在の平均寿命(男性81.05歳、女性87.09歳)を考慮すると、退職後の人生は20年近くにわたります。そのため、退職金だけでは老後の生活を十分に支えることが難しいかもしれません。
退職金を運用し、資産を増やすことができれば、より安心して老後の生活を送ることができるでしょう。
公的年金では生活費が足りない可能性がある
公的年金だけでは老後の生活費が不足する可能性も、退職金を運用した方がいい理由の一つです。
厚生労働省の「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、年金の平均受給額は月14万4,982円です。しかしこの額だけでは、老後の生活費をまかなうのは難しいかもしれません。
実際、総務省統計局の「家計調査年報(家計収支編)2022年(令和4年)」によると、65歳以上の年金生活の単身世帯や夫婦世帯の家計収支は、毎月2万円を超える赤字となっています。
退職金を運用することで、公的年金では不足する老後の生活費を補える可能性があります。
インフレによりお金の価値が下がる可能性
インフレは、モノやサービスの価格が継続的に上昇し、相対的にお金の価値が下がる現象です。原材料の高騰や通貨安などの要因により、商品やサービスの価格が上昇しており、昔と同じ金額で同じ商品やサービスを購入することが難しくなっています。
将来もインフレが続けば、退職金の価値も現在とは違うものになるでしょう。日本銀行の「生活意識に関するアンケート調査」によれば、物価が「かなり上昇した」と回答した人は6割を超え、「少し上昇した」と合わせると9割以上にもなります。
さらに、将来的に「かなり上昇する」「少し上昇する」と予測した人も8割を超えました。
今後もインフレが続く可能性があることを考慮し、対策を講じておくことが大切です。
老後の収入確保が難しい
老後の収入確保が難しいことも、退職金を運用した方がいい理由の一つです。
内閣府の「令和4年 高齢者の健康に関する調査結果」によれば、65歳以上の高齢者(施設入所者は除く)で、健康状態が「あまり良くない」「良くない」と回答した割合が24.6%でした。これはつまり、4人に1人が健康状態が良くない可能性があるということです。この割合は年齢が上がるにつれて増加する傾向があります。
高齢者は健康問題に加え、現役時代と同じような仕事に就くことが難しい状況です。希望する職種や勤務形態で働くことができない場合があります。
同調査によると、最も一般的な勤務形態は「パート・臨時の雇用者」で、割合は38.8%です。また、1週間の労働時間に関しては20時間未満が31.3%で最も多いです。
健康状態や働く時間、働く形態などから、高齢になると収入を確保することがますます難しくなります。そのため、資産運用などの労働以外の収入源を構築することが必要です。
安全に退職金の運用をするための注意点

退職金を運用する際には、全額を投資に回さない、長期で運用する、分散投資を行うことなどが重要です。これらのポイントを押さえることで、損失リスクを軽減し、安全性を高めることができます。
ここでは、退職金を安全に運用するための注意点について見ていきましょう。
退職金の全額運用は避ける
退職金を安全に運用するための注意点の一つは、全額を運用に回さないことです。運用によって資産が増える可能性はありますが、タイミングによっては損失を被り、資産が減少するリスクもあります。退職金をすべて運用に回し、多額の損失が出ると、老後生活の資金計画が大きく狂う可能性があります。
退職金以外に十分な貯金がある場合は影響は少ないかもしれませんが、そうでない場合は非常に大きな問題です。
リスクの低い運用商品を選んでも、損失リスクは避けられません。そのため「運用に失敗するかもしれない」という考えを持ちながら、退職金のうちいくらを投資に回すのかを慎重に決めることが大切です。
「資産のうち、●割を投資に回す」といった明確なルールは存在しないため、資産状況、今後の必要資金、運用目的などを総合的に考慮して、自分自身で投資に回す金額を決める必要があります。
参考までに、以下は日銀が公表している日本、米国、ユーロエリアにおける家計の金融資産構成です。
| 日本 | 現金・預金:54.2%保険・年金・定型保証:26.2%株式等:11.0%投資信託:4.4%債務証券:1.3% その他計:2.9% |
| 米国 | 現金・預金:12.6%保険・年金・定型保証:28.6%株式等:39.4%投資信託:11.9%債務証券:4.9% その他計:2.7% |
| ユーロエリア | 現金・預金:35.5%保険・年金・定型保証:29.1%株式等:21.0%投資信託:10.1%債務証券:2.2% その他計:2.1% |
現金・預金の割合は、日本では50%を超えていますが、米国では12.6%、ユーロエリアでは35.5%と低くなっています。
一方で、これらの地域では、株式や投資信託の割合が高くなっており、特に米国は資産運用に非常に積極的であることが伺えます。
長期で運用する
退職金を運用する際には、長期的な視点を持つことが大切です。
長期投資では、毎日チャートを確認する必要がないため、日々の値動きに一喜一憂することが減ります。また、短期投資に比べて取引回数が少なくなるため、売買コストを抑えることが可能です。さらに、長期投資は積立投資との相性が良く、複利効果を得やすいというメリットもあります。
例えば、スキャルピングやデイトレードなどの短期売買では、チャートを頻繁にチェックする必要があり、値動きに一喜一憂しやすく、ストレスの原因となることが多いです。結果として、日常生活の多くの時間を投資に費やすことになり、引退後にやりたかったことや家族との時間が犠牲になるかもしれません。
30年や40年といった超長期の計画を立てる必要はありませんが、1年未満など、短期間での運用計画は避けた方がよいでしょう。スキャルピング、デイトレード、スイングトレードといった短期売買で安定した収益を出し続けるには、豊富な知識や経験、ノウハウが必要です。
金融庁や日本証券業協会も、長期投資、積立投資、分散投資を推奨しています。
参考:金融庁「資産形成の基本」
日本証券業協会「NISAで長期・積立・分散投資がいいさ!」
分散投資でリスクを軽減する
退職金を運用する際には、リスクを分散させることが重要です。一つの投資先に資産を集中させると、その投資先が暴落した場合に大きな損失を被る可能性があります。
しかし、複数の投資先に資産を分散させれば、一つの投資先が暴落しても全体のリスクが軽減されます。著名な投資家たちも、ほとんどが資産を一つの投資先に集中させることを避けています。
個人向け年金、債券(国内債券、外国債券)、株式、投資信託、不動産、コモディティなど、さまざまな投資先に資産を分散させ、価格の暴落に対してリスクヘッジすることが大切です。投資の世界では「卵を一つのかごに盛るな」という言葉があるように、分散投資はリスク管理の基本と言えます。
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)でも分散投資を推奨しています。
参考:年金積立金管理運用独立行政法人「分散投資の意義③卵を一つのかごに盛るな」
非課税制度を利用する
非課税制度(NISA)を活用することも、退職金の運用において重要なポイントです。
NISAは、個人投資家向けの非課税制度です。通常、株式投資や投資信託から得た利益には、20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税金がかかります。
しかし、NISAを利用すると、運用益が非課税となるため、資産形成を効率的に進めることが可能です。
例えば、株式投資で10万円の利益が発生した場合、通常は20.315%(約2万3,150円)の税金がかかるため、最終利益は約7万9,685円になります。しかし、NISAを利用する場合は、税金が0円となるため、最終利益は10万円になります。
NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があり、それぞれの詳細は以下のとおりです。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
|---|---|---|
| 非課税保有期間 | 無制限 | 無制限 |
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有限度額 | 1,800万円※成長投資枠は内数1,200万円 | |
| 投資対象商品 | 一定の基準を満たした投資信託 | 上場株式、投資信託など |
NISA口座は、銀行や証券会社で無料で開設することができます。非課税制度(NISA)をうまく活用して、より多くの資産を築きましょう。
ハイリスク・ハイリターンの投資をしない【安全な運用】
退職金を運用する際には、ハイリスク・ハイリターンの投資は避けるべきです。
ハイリスク・ハイリターンの投資は、大きな利益を得られる可能性がある一方で、大きな損失を被るリスクも高いため、退職金の大半をあっという間に失う危険性があります。
一般的に、ハイリスク・ハイリターン型の投資には、FX、仮想通貨(暗号資産)、先物取引、信用取引などがあります。
資産に余裕があり、十分な老後資金が確保できている場合は、ハイリスク・ハイリターンの投資を検討してもよいでしょう。しかし、そうでない場合は、リスク管理の観点から、ローリスク・ローリターンやミドルリスク・ミドルリターンの投資を選ぶべきです。
特に投資初心者の場合は、リスクを抑えながら運用することが重要です。
経験を積み、多くのノウハウを得て資産に余裕ができた段階で、ハイリスク・ハイリターンの投資を検討しましょう。 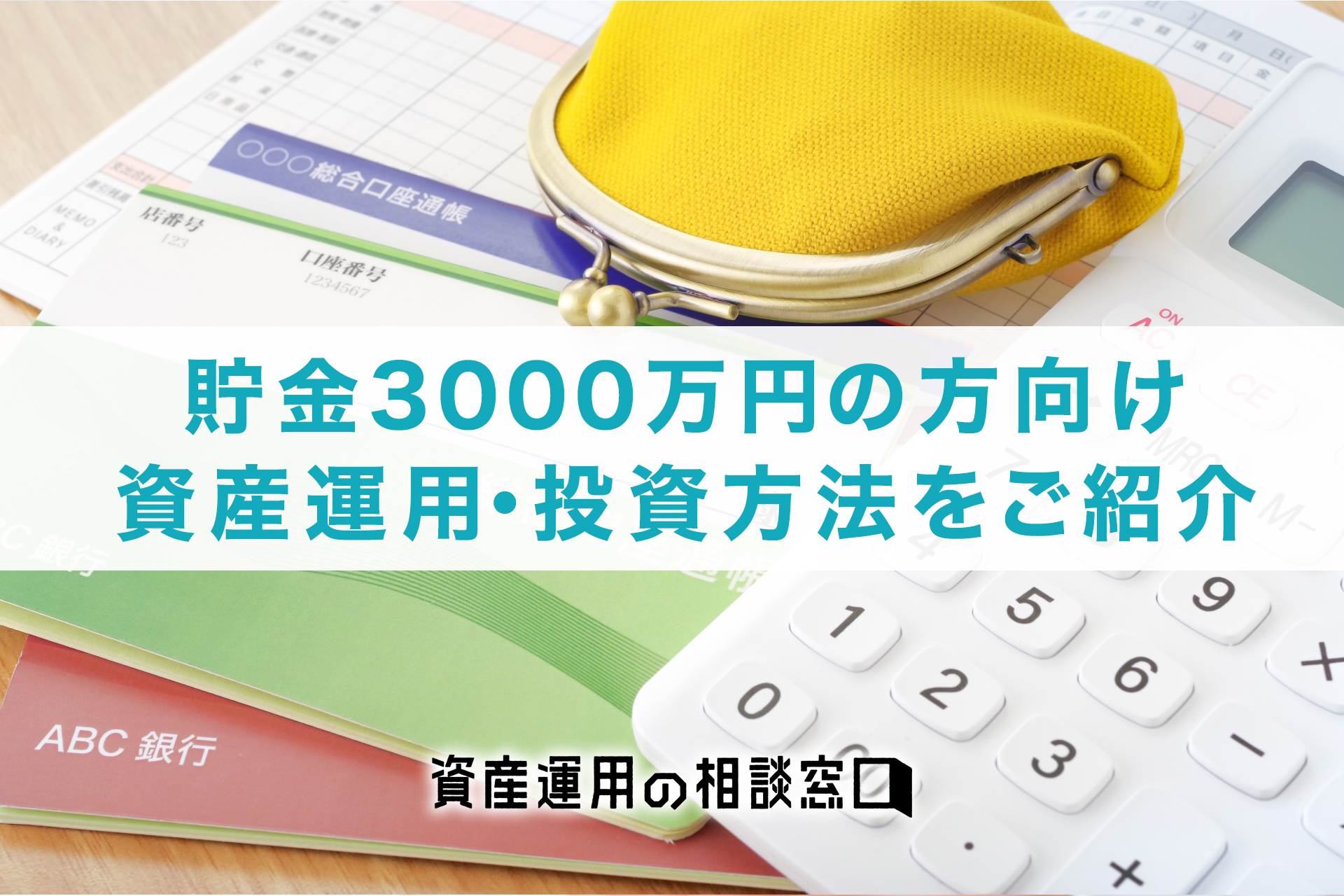
退職金のおすすめ運用方法ランキング6選

退職金の運用には、退職金定期預金、個人向け国債、株式投資、投資信託などが選択肢として挙げられます。
運用方法のランキングを把握することで、自分に最適な退職金の運用方法を見つけやすくなります。
ここでは、退職金のおすすめ運用方法ランキングを紹介しますので、参考にしてください。
①個人年金保険
退職金の運用方法として、個人年金保険はおすすめです。
個人年金保険は、私的年金の一つで、公的年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)だけでは不足する老後資金を補填します。特定の年齢に達したときに、これまで支払った保険料に応じた年金を受け取れる仕組みです。
貯金が得意でない人でも、保険料の支払いが強制されるため、老後資金を計画的に用意できます。
また、年間の保険料に応じて生命保険料控除(個人年金保険料控除)が適用され、所得税や住民税の軽減が可能です。
個人年金保険は死亡保険とは異なり、健康状態に不安がある方でも加入しやすい特徴があります。
厚生労働省の「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、年金の平均額は月14万4,982円です。「ねんきん定期便」などを利用して将来の年金受給額を確認することをおすすめします。
参考:国税庁「生命保険料控除」
日本年金機構「大切なお知らせ、「ねんきん定期便」をお届けしています」
②退職金定期預金
退職金の運用方法として、退職金定期預金もおすすめです。退職金定期預金は、退職金専用に用意された定期預金であり、金利が通常の普通預金や定期預金よりも高く設定されています。
主な銀行の退職金定期預金の金利は、以下のとおりです。
| 愛知銀行 | 京葉銀行 | 広島銀行 | |
|---|---|---|---|
| 普通預金金利 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| 定期預金金利 | 0.025%〜0.2% | 0.025%〜0.2% | 0.025%〜0.3% |
| 退職金定期預金金利 | 定期預金金利+0.3%〜0.5% | 0.7% | 0.025%+0.05%〜0.8% |
ただし、「退職金を受け取ってから1年以内」など、預入期間に制限があり、預入金額も最低300万円〜1,000万円程度に設定されていることが多いです。
また、取り扱う金融機関が限られているため、普段利用している金融機関で退職金定期預金が提供されていない可能性があります。
一部の金融機関では、投資信託と定期預金を組み合わせた商品が販売されています。
③貯蓄型保険
退職金の運用方法として、貯蓄型保険もおすすめです。
貯蓄型保険は、貯蓄性が高い保険で、終身保険や養老保険、学資保険などがあります。
保険料の一部が積み立てられるため掛け捨てにはならず、解約時には解約返戻金を受け取ることができます。また、払い込んだ保険料は生命保険料控除の対象となり、所得税や住民税の軽減が可能です。
緊急時には、解約返戻金の一定の範囲内で貸付を受けられる契約者貸付を利用することもできます。
ただし、貯蓄型保険は掛け捨て型より保険料が高くなる傾向があるため、注意が必要です。
「万一に備えながら積立もしたい」という方に特におすすめの商品です。
④個人向け国債
退職金の運用におすすめなのが、個人向け国債です。
個人向け国債とは、国が資金調達を目的として個人向けに発行する債券のことです。
保有期間中には半年ごとに利子が支払われ、満期には元本が返還されます。
国が発行体であるため、破綻リスクが低く、安全性が高いのが特徴です。金融機関の窓口やインターネットで、手軽に1万円から購入することができます。
個人向け国債には、「変動金利型10年満期」「固定金利型5年満期」「固定金利型3年満期」という3つの商品があります。それぞれの詳細は、以下のとおりです。
| 変動金利型10年満期 | 固定金利型5年満期 | 固定金利型3年満期 | |
|---|---|---|---|
| 満期 | 10年 | 5年 | 3年 |
| 金利タイプ | 変動金利 | 固定金利 | 固定金利 |
| 表面利率(税引き後) | 0.69%(0.5498265%) | 0.59%(0.4701415%) | 0.4%(0.3187400%) |
※財務省「個人向け国債」をもとに筆者が作成
発行から1年が経過すると、個人向け国債は中途解約が可能です。
ただし、中途換金する場合には、「直前2回分の利子(税引き前)相当額×0.79685」が差し引かれるため注意してください。
個人向け国債は大きなリターンは見込めませんが、安全性を求める方にはおすすめです。
⑤株式投資
株式は、企業が資金調達を目的に発行する有価証券です。株式投資で得られる利益は、大きく分けて「売却益」と「配当金」の2つです。
株価が購入時よりも高くなったときに売却することで売却益(値上がり益)を得ることができます。
また、株式を保有している間に、年に1〜2回程度配当金が支払われる場合もあります。
つまり、配当金を受け取りながら、売却益も狙うことが可能です。
さらに、企業によっては、自社製品やカタログギフト、商品券、クオカードなどの株主優待を提供しているところもあります。
一部の銘柄は最低投資金額が100万円を超えますが、10万円以下で投資できる銘柄も多く、「少額から始めたい」という方でも安心です。
銘柄の選び方は投資家によってさまざまで、普段利用している企業、業績好調な企業、チャートの形が良いもの、高配当、魅力的な優待などが挙げられます。
NISAを活用すれば、非課税で運用することも可能です。
日本取引所グループの「その他統計資料」によれば、2024年5月のプライム市場における株式平均利回り(加重平均利回り)は2.03%となっています。
⑥投資信託
退職金の運用には投資信託がおすすめです。投資信託は、複数の投資家から資金を集めて株式、債券、不動産などに分散投資する商品です。投資信託運用会社が商品をつくり、銀行や証券会社などの販売会社が資金を集め、信託銀行が資産を管理します。
投資信託は、少額からでも投資が可能です。一部の証券会社では100円から投資ができるので、気軽に始められます。
また、1つの投資信託に投資するだけで分散投資が可能です。個人投資家が手に入りにくい商品にも、投資信託を通じて投資することができます。投資のプロが運用するため、投資初心者でも安心です。
金融機関や証券会社によっては、クレジットカードで積立投資ができ、ポイントを貯めることができます。
ただし、投資信託は、購入時に購入時手数料、運用中に信託報酬、解約時に信託財産留保額と呼ばれる手数料が発生します。

退職金の資産運用が不安ならプロに相談がおすすめ

退職金の運用に不安を感じる場合は、プロに相談することがおすすめです。
知識や経験、ノウハウが豊富なので資産運用に関する有益なアドバイスや、条件に合った投資商品を提案してくれます。
また、安定的な収益を得る適切なポートフォリを組むためには専門家の意見はとても重要になります。
ただし、相談先には銀行、証券会社、IFA、保険会社があり、それぞれ特徴が異なるため事前に理解しておくことが大切です。ここでは、各相談先の特徴について見ていきましょう。
銀行

メガバンクや地方銀行など、多くの銀行では各店舗で資産運用に関する相談を受け付けています。お金に関する豊富な知識を持つ専門スタッフが、資産運用の不安や疑問に答え、適切な商品を提案してくれます。
銀行は社会的信用性が高いため、個人で活動する専門家よりも安心感を得やすいのが特徴です。普段から利用している銀行であれば、気軽に相談できるメリットもあります。
また、一部の銀行では、自社商品を運用した場合に独自のポイントが貯まるなどの特典が用意されています。
ただし、銀行によっては資産運用の相談に対応していない場合があるため、事前に確認が必要です。また、取り扱う商品が限られており、銀行側にとって都合の良い商品を提案される可能性があることにも注意が必要です。
証券会社

店舗を構えている対面型の証券会社では、資産運用に関する相談を受け付けている場合があります。
証券会社は資産運用に関する豊富な情報を持っているため、有益なアドバイスを受けることができる可能性が高いです。また、株式、債券、REIT、投資信託、ETF、コモディティなど、幅広い商品を取り扱っているため、自分に最適な選択肢が見つかる可能性があります。
一部の証券会社では、ポイントやキャッシュバックなどの特典やキャンペーンが提供されることもあります。
ただし、銀行ほど店舗数は多くありません。自宅や勤務先から距離があり相談しに行くのが難しい場合があるため、事前に店舗の場所を確認しておくことが重要です。
IFA

IFA(Independent Financial Advisor)は、独立系ファイナンシャルアドバイザーのことです。相談者の資産状況やライフステージに応じて、適切な運用プランを提案する資産運用の専門家で、売買支援を行うこともあります。
IFAは個人で活動しており、複数の金融機関や証券会社と業務委託契約を結んでいます。特定の機関に属していないため、中立的な立場でアドバイスを提供できるのが大きな魅力です。転勤がないため、長期的なサポートが期待できます。
ただし、相談が有料の場合があるため、事前に費用を確認することが必要です。
また、個人で活動しているため、銀行や証券会社と比べると社会的信用度や知名度は低いと言えます。
保険会社

保険会社では、将来の目標やライフプランに合わせて資産運用や保険商品の提案を受けることができます。
営業担当者が自宅を訪問したり、外出先で気軽に相談できます。貯蓄型保険など、万一に備えながらお金を積み立てたい人に特におすすめです。
ただし、営業担当者にはノルマがあるため、自社の都合に合った商品を提案される可能性があります。また、保険には詳しくても、資産運用に関しては詳しくない場合があるので注意が必要です。
退職人の運用についてまとめ
ここまで説明したように、退職金を運用することで不足しがちな老後資金を補い、より余裕のある生活を送れる可能性があります。ただし、資産運用には元本割れのリスクが伴うため、分散投資などのリスク管理が重要です。
株式投資や個人向け国債、貯蓄型保険など、それぞれに特徴があるため、自分に合った方法で運用することが大切です。
資産運用がわからない・不安だからという理由で退職金の運用をしない選択肢はインフレにより資産の目減りのリスクもあります。資産運用・NISAの相談に関して不安や疑問がある場合は、まず専門家に相談してから始めることをおすすめします。