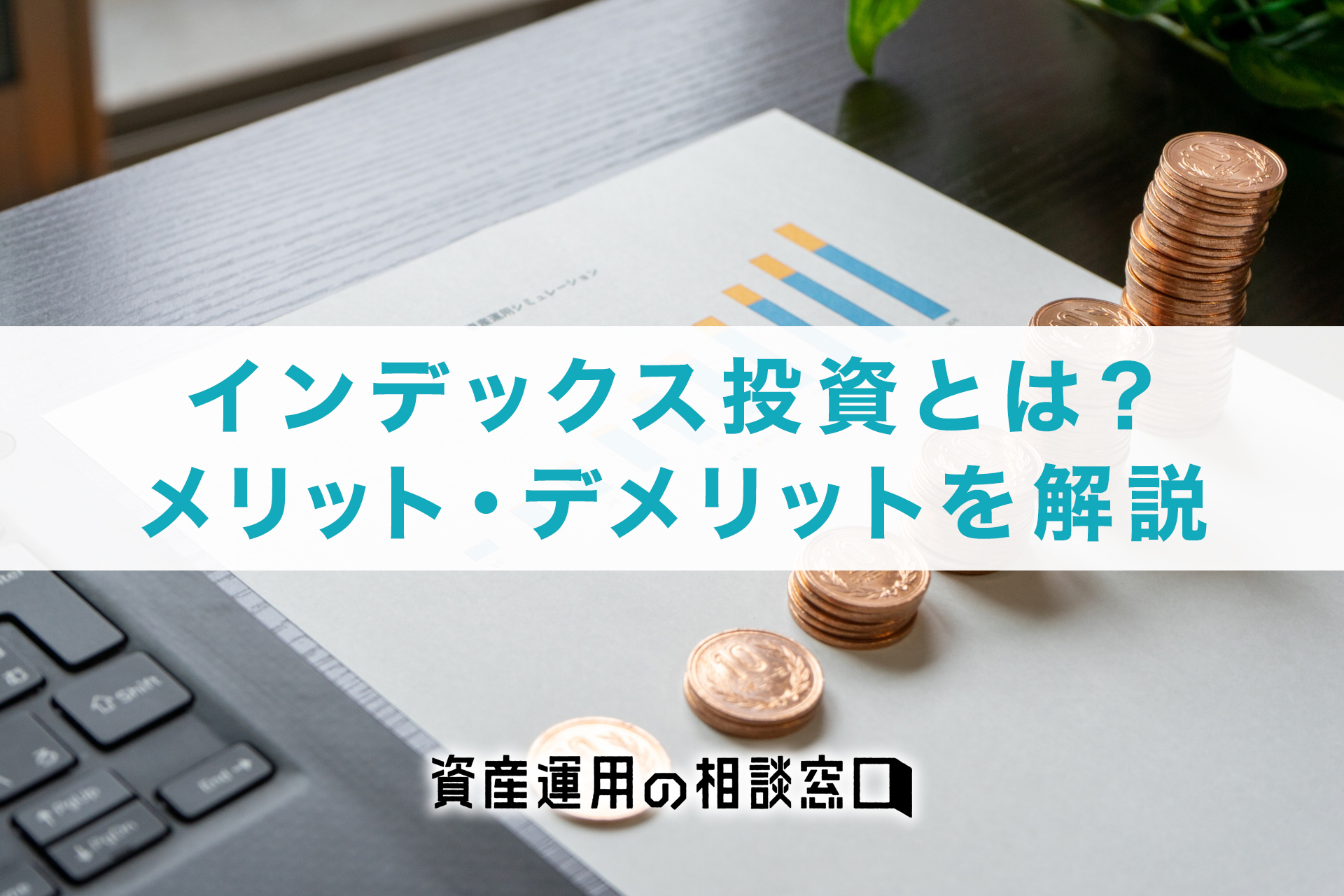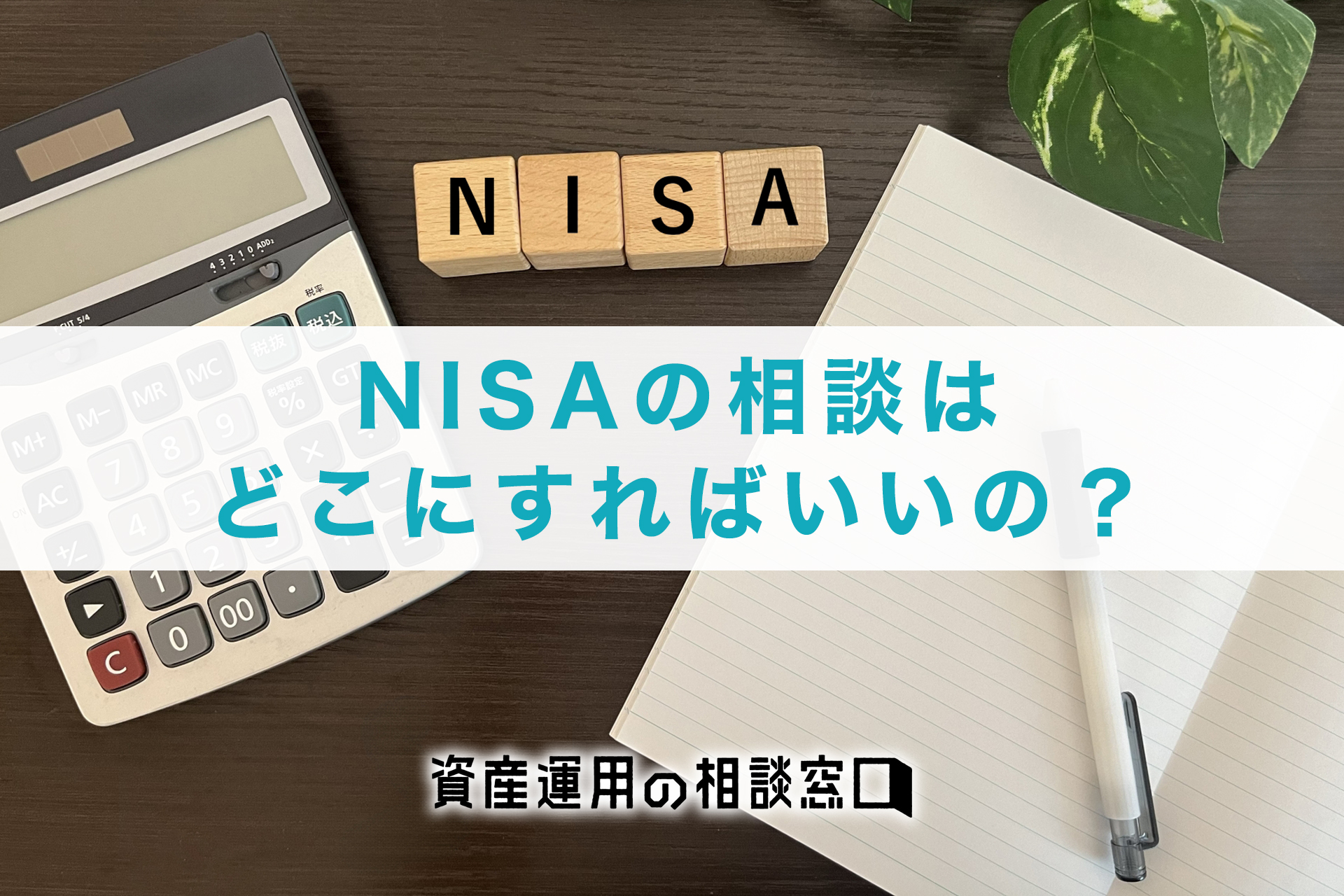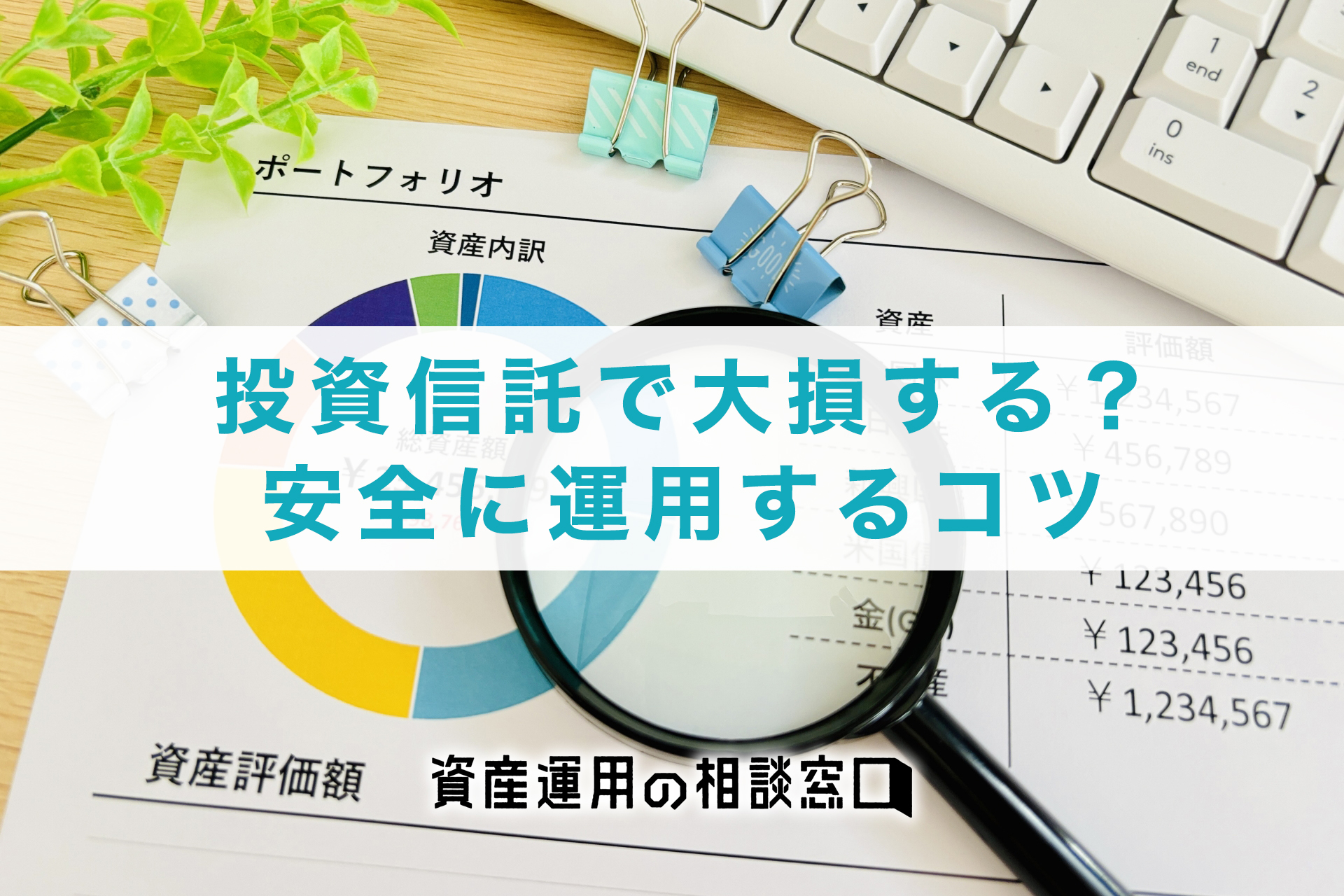「インデックス投資とは何?インデックスファンドやETFとはどう違うの?」「インデックス投資とアクティブ投資の違いは?どちらがおすすめ?」といった疑問を持っている方も多いでしょう。
インデックス投資は、分散投資によりリスクを軽減でき、少額から始められる初心者に人気の投資方法です。個別銘柄への投資が難しいと感じる方にとっては、最適な選択肢となる可能性があります。
この記事では、インデックス投資の意味や特徴、仕組み、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。 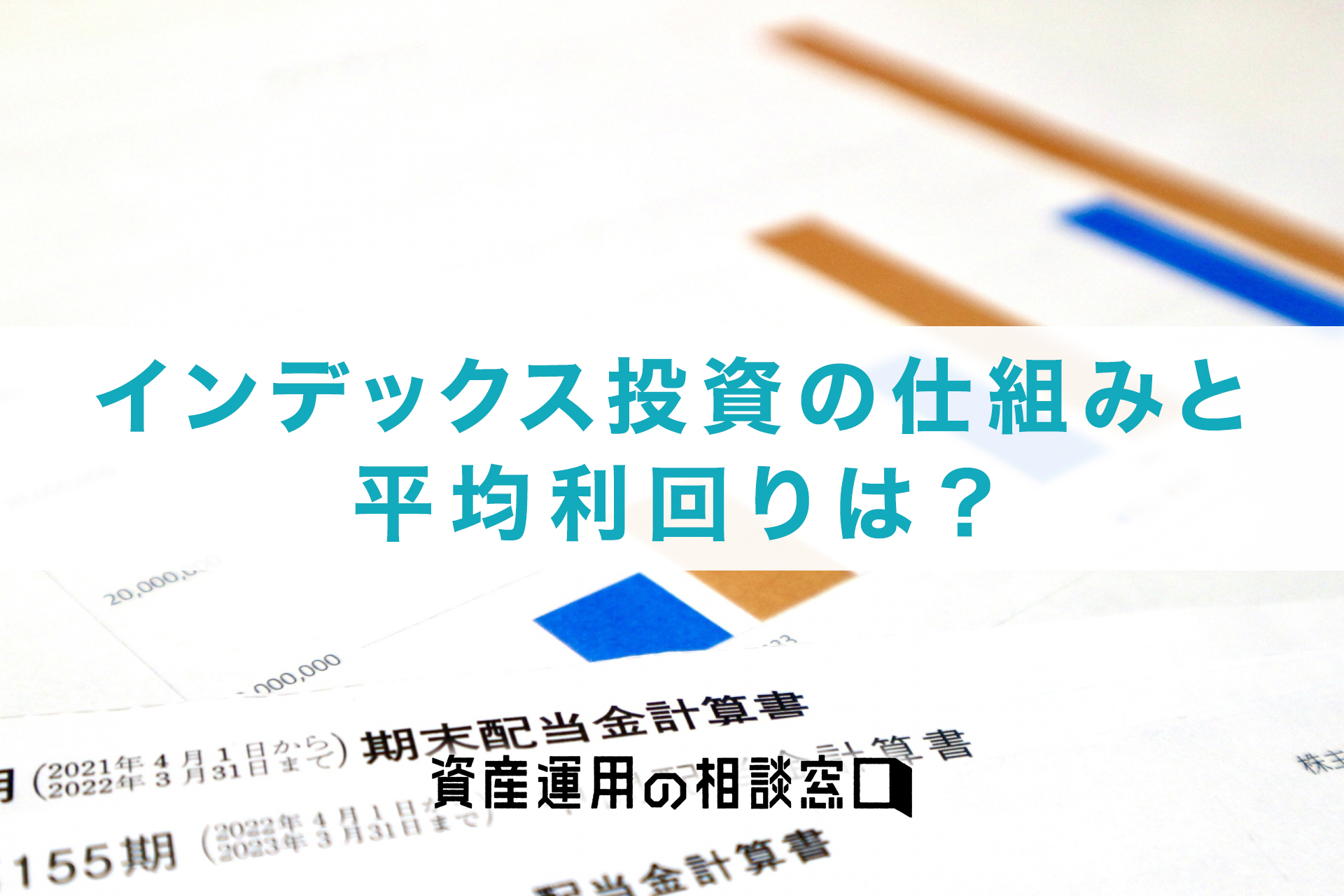
インデックス投資とは?

インデックス投資とは、日経平均株価やNYダウなど、市場全体の値動きを示す指数に連動することを目指す投資手法です。
ベンチマークとするインデックスに含まれる銘柄を同じ割合で購入することで、その指数の値動きを反映させます。
インデックス投資の特徴は、値動きがわかりやすく、分散投資によってリスクを軽減できる点です。また、少額から始められる商品や積立投資に適した商品が多いことも魅力です。
インデックス投資に該当する商品には、投資信託やETF(上場投資信託)などがあります。
投資におけるインデックスの意味
インデックスとは、市場全体の値動きを示す指数のことです。
代表的なインデックスには、日経平均株価(日経225、日経平均)、TOPIX(東証株価指数)、NYダウ(ダウ平均株価)、S&P500指数、ナスダック総合指数などがあります。
例えば、日経平均株価(日経225、日経平均)は、東証プライム市場に上場する約2,000の銘柄のうち、市場流動性や業種を考慮して選ばれた225銘柄の株価をもとに算出される指数です。
積水ハウス(建設)、サッポロホールディングス(食品)、トヨタ(自動車)、伊藤忠商事(商社)、ニトリホールディングス(小売業)などの有名企業が採用されています(2024年7月13日時点)。日経平均株価は日本経済新聞社によって発表されていて、立会取引の時間帯(前場9時〜11時30分、後場12時30分〜15時)に5秒ごとに算出されます。
インデックスの動きを追うことで、市場全体の動向を把握することが可能です。例えば、日経平均やTOPIXを見ることで、東証プライム市場全体の相場が上昇しているのか、下落しているのかを確認できます。また、インデックスは基準となるため、個別銘柄と比較することで、その銘柄のパフォーマンスを評価することも可能です。
世界には非常に多くのインデックスが存在しています。
インデックスファンドとの違い
インデックスファンドとは、特定のインデックスに連動する投資成果を目指す投資信託のことです。
インデックス投資は特定のインデックスに連動する「投資方法」を指し、インデックスファンドは「投資商品(投資信託)」を指します。
代表的なインデックスファンドには、以下のようなものがあります。
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・ニッセイ外国株式インデックスファンド
・i FreeNEXT FANG+インデックス
・SBI・V・S&P500インデックスファンド(SBI・V・S&P500)
・楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI)
・インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式)
・日経225ノーロードオープン など
また、投資信託とは、多くの投資家から集めた資金を専門家が運用する金融商品のことです。投資信託の主なメリットとデメリットは、以下のとおりです。
インデックスファンドは、投資初心者でも始めやすく、とても人気があります。多くの人が非課税制度であるNISA(新NISA)を活用し、長期的な視点でインデックスファンドを運用しています。
インデックスの主な分類とは?
インデックスは、資産、地域、国、通貨などによって分類されます。主な分類は、以下のとおりです。
| 主な分類 | 主な商品 |
|---|---|
| 資産別 | ・日本株式・外国株式・日本債券・外国債券・日本REIT・外国REIT・コモディティなど |
| 地域別 | ・国内(日本)・全世界・アメリカ地域・ヨーロッパ地域・アジア・パシフィック地域・中東・アフリカ地域など |
| 国別 | ・先進国・新興国など |
| 通貨別 | ・日本円・米ドル・ユーロ・ポンド・豪ドルなど |
これらの分類を理解することで、資産運用において資産クラスを分散できます。また、同じ資産クラス内で複数の投資商品を持つことで、リスクを軽減することができます。
例えば、TOPIXに連動する投資信託と、S&P500指数に連動する投資信託で運用すれば、国内とアメリカの多くの銘柄に分散投資が可能です。
また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスとJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドに連動する商品に投資すれば、新興国の株式と債券をある程度カバーできます。
先進国の株式と債券をカバーしたい場合は、MSCIコクサイ・インデックスやFTSE世界国債インデックスをベンチマークとするインデックス投資を検討できます。
インデックスの代表例
代表的なインデックスと、内容・主な銘柄構成は以下のとおりです。
| インデックス | 内容・主な銘柄構成 |
|---|---|
| 日経平均株価 | 東証プライム市場に上場する約2,000銘柄のうち、市場流動性等を考慮して選定された225銘柄の株価をもとに算出される指数です。 |
| TOPIX(東証株価指数) | 東証に上場する銘柄を幅広く対象としています。基準日(1968年1月4日)の時価総額を100として、それ以降の時価総額を指数化しています。 |
| TOPIX 1000 | TOPIX対象銘柄のうち、売買代金と時価総額が高い1,000銘柄で構成される株価指数です(時価総額加重型)。 |
| JPX日経400(JPX日経インデックス400) | 日本経済新聞社とJPXグループが公表している指数で、東証に上場する銘柄から一定の基準を満たす400銘柄が選定されています。主な基準には、債務超過や営業赤字がない(過去3期内)などがあり、「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成されます。 |
| ダウ平均株価(NYダウ) | ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価のことです。ニューヨーク証券取引所とナスダック市場に上場する優良な30銘柄で構成されています。アップル、アマゾン、コカ・コーラなど。 |
| S&P500指数 | S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社が公表する指数で、ニューヨーク証券取引所とナスダック市場に上場する銘柄のうち、500銘柄を選定し、時価総額にもとづいて算出されています。 |
| NASDAQ(ナスダック)指数 | ナスダックに上場する銘柄のうち、100銘柄を選定して時価総額加重平均で算出した「NASDAQ100指数」と、すべての銘柄を対象に時価総額加重平均で算出した「NASDAQ総合指数」があります。ナスダックの上場銘柄には、マイクロソフト、アップル、エヌビディアなどがあります。 |
| MSCI コクサイ・インデックス | モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社が公表するこの指数は、先進国(日本を除く)22カ国の大型株・中型株の上場銘柄から選定された約1,300銘柄で構成されています。時価総額で市場の約85%をカバーしています。 |
| MSCIエマージング・マーケット・インデックス | 新興国の株価動向を示す指数で、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社が公表しています。新興国24カ国に上場する大型株・中型株から選定された約1,400銘柄で構成されています。時価総額で市場の約85%をカバーしています。 |
| MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス | 先進国23カ国と新興国24カ国に上場する大型株・中型株から選定された銘柄で構成されています。指数は時価総額加重平均で算出されるため、時価総額の大きいアメリカの銘柄が最も多く含まれています(約60%)。世界の株式を網羅する指数です。 |
| NOMURA-BPI総合指数 | 国内で発行された公募固定利付債券の市場動向を示す代表的な指数です。野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティングが公表しており、時価総額加重平均で算出されています。構成銘柄は毎月見直されています。 |
| FTSE世界国債インデックス | 先進国の国債市場の動向を示す指数です。以前はシティ世界国債インデックスという名称でした。国債の総合投資利回りを市場の時価総額で加重平均して算出しています。 |
| JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド | 新興国の国債市場の動向を示す指数です。J.P.モルガン・セキュリティーズが算出しています。 |
| 東証REIT指数 | 東証に上場するREIT(不動産投資信託)銘柄を対象とし、時価総額加重平均で算出された指数です。基準日(2003年3月31日)の時価総額を100として、それ以降の時価総額を指数化しています。 |
| S&P先進国REIT指数 | 先進国のREITの動向を示す指数で、S&Pダウジョーンズ・インデックス社が公表しています。一定の基準(時価総額や流動性など)を満たす銘柄を対象に、時価総額加重平均で算出されています。 |
インデックス投資では、このような指数に連動する投資成果を目指します。
インデックス投資のメリットとは?

インデックス投資のメリットには、分散投資によってリスクを軽減できることや、少額から始められる点があります。
これらのメリットを理解することで、インデックス投資が自分に合っているかどうかを判断しやすくなります。
ここでは、インデックス投資のメリットについて見ていきましょう。
分散投資によるリスク軽減
インデックス投資のメリットの一つは、分散投資によってリスクを軽減できることです。
分散投資とは、投資資金を一つの商品に集中させず、複数の商品に分散して投資する方法です。一つの商品に全額投資すると、その商品の価値が暴落した場合に資産が大きく減少してしまいます。
しかし、複数の商品に分散投資していれば、他の商品が値上がりすることで資産の大幅な減少を防ぐことが可能です。「卵は一つのカゴに盛るな」という投資に関する格言は有名です。
インデックス投資は、ベンチマークとする指数の構成銘柄に投資することで、その指数の値動きに連動させることを目指します。例えば、日経平均株価に連動させる場合、日経平均株価を構成する以下のような銘柄に投資します。
・ニッスイ
・積水ハウス
・清水建設
・ニチレイ
・トヨタ
・ニトリ
・イオン
・ファーストリテイリング
・三菱UFJ
・リクルート など
※2024年7月13日時点
インデックス投資は複数の銘柄に分散投資するため、リスクの軽減が可能です。金融庁やGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)も、資産運用において分散投資を推奨しています。
参考:金融庁「資産形成の基本」
初心者でも手を出しやすい
インデックス投資は、初心者にも手を出しやすい投資方法として人気があります。その理由は以下のとおりです。
・投資のプロが運用する
・値動きがわかりやすい
・分散投資が可能
・NISAも利用できる
インデックスファンドやETF(上場投資信託)は、投資家から集めた資金をプロが運用します。銘柄の選定や入れ替えはすべてプロが行うため、個人投資家は難しいことを考えずに済み、手間もほとんどかかりません。個別銘柄のように企業の業績や財務、需給などをチェックする時間も省けます。
また、日経平均株価、TOPIX、NYダウ、S&P500などの指数に連動するため、値動きがわかりやすいです。手軽に分散投資ができ、NISAの利用も可能です。
初心者でも始めやすいことは、インデックス投資のメリットの一つです。
少額から始められる
少額から始められることもインデックス投資の大きなメリットです。
例えば、個別株に投資する場合、数万円〜数十万円の資金が必要となるため、手元資金が少ない場合は希望する銘柄に投資できないことがあります。
一方で、インデックス投資は100円程度から始められます。多くのインデックスファンドは100円から購入できるので、少額の資金でも安心して投資を始めることが可能です。さらに、証券会社によっては自動積立も設定できます。
また、非課税制度であるNISAのつみたて投資枠を活用すれば、インデックスファンドの運用益(売却益や分配金)が非課税となり、効率的に資産を運用できます。通常、インデックスファンドの運用益には20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税金がかかりますが、NISAを利用すると税金がかかりません。
つみたて投資枠の年間投資枠は120万円までで、非課税保有期間は無制限です。対象となるのは金融庁の基準を満たす投資信託です。
インデックス投資は少額から始められるため手軽に取り組めて、NISAを活用した積立投資などの運用方法も検討できます。
手数料を安く抑えることができる
インデックス投資は、手数料を抑えられるというメリットがあります。
例えば、投資信託には以下の手数料がかかります。
・購入時手数料:購入時にかかる手数料(手数料なしの商品も多い)
・信託報酬:投資信託を保有している間にかかる手数料
・信託財産留保額:解約時にかかる手数料
購入時手数料が無料(ノーロード)の商品は多数あります。また、信託報酬が1%以下に設定されている商品も多く見られます。
以下は、主なインデックスファンドの手数料です。
| インデックスファンド | 購入時手数料 | 信託報酬(年) | 信託財産留保額 |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | なし | 0.05775%以内 | なし |
| SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | なし | 0.0938%程度 | なし |
| 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | なし | 0.55% | 0.1% |
| 大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | なし | 0.7755% | なし |
| ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | なし | 0.2035% | なし |
参考までに、インデックスファンドと対比される主なアクティブファンドの手数料は以下のとおりです。
| アクティブファンド | 購入時手数料 | 信託報酬(年) | 信託財産留保額 |
|---|---|---|---|
| ひふみプラス | なし | 1.078%以内 | なし |
| マネックス・アクティビスト・ファンド(日本の未来) | なし | 2.2%+成功報酬 | 0.3% |
| 三井住友DS・海外株式ETFファンド | なし | 1.12%〜1.22%程度 | なし |
| イーストスプリング・インド・コア株式ファンド(+αインド) | なし | 0.9905%程度 | 0.3% |
| 三井住友DS-大和住銀DC海外株式アクティブファンド | なし | 1.782% | なし |
投資信託によって手数料は異なりますが、インデックスファンドは一般的に手数料が低い傾向があります。
インデックス投資のデメリットとは?

インデックス投資のデメリットを理解することも大切です。
デメリットを把握することで、インデックス投資が自分にとって最適な選択かどうかを見極めることができます。また、適切なリスク対策を取ることが可能になります。
それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。
短期運用では利益が出ない可能性がある
インデックス投資は、一般的に中長期的な視点で利益を目指す方法であり、短期間で大きなリターンを狙うのには向いていません。
個別銘柄では短期間で大きく値動きすることがありますが、インデックス投資は市場全体に連動するため、短期的な値動きはあまり大きくなりません。
そのため、短期間での売買で大きなリターンを狙いたい場合は、個別銘柄を検討したほうがよいでしょう。
インデックス投資をする際は、「将来の老後資金を形成する」「10年後に●万円に増やす」といった、数年〜数十年の長期的な視点で大きなリターンを目指すことが大事です。
株価指数以上のハイリターンは期待できない
インデックス投資は、日経平均株価、TOPIX、S&P500などに連動することを目指し、それらの指数を構成する銘柄に投資します。そのため、ベンチマークとなる指数と同様の値動きをするのが特徴です。
例えば、日経平均株価に連動するインデックス投資では、日経平均株価の動きに追随します。インデックス投資は、市場全体の値動きを上回るリターンを狙うアクティブ運用とは異なり、指数を超えるハイリターンは期待できません。
そのため、インデックス投資で運用する際には、ベンチマークとなる指数の動きを事前に確認しておくことが大切です。指数の変動が少ない場合、得られるリターンも限られる可能性があります。
インデックス投資は、指数を上回るハイリターンは期待できないというデメリットがあることを理解しておきましょう。
元本割れの可能性がある
インデックス投資は分散投資によってリスクを軽減できますが、利益が保証されているわけではありません。指数が下落すると損失が発生する可能性もあるため、注意が必要です。
例えば日経平均株価は、大きな調整があり、1日で1,000円程度下がることも珍しくありません。また、現在株価が上昇していても、世界経済のリセッションなどがきっかけで長期的な下落トレンドに入る恐れもあります。
他の投資商品にも言えますが、投資には元本割れのリスクがあるため、リスク管理や資金管理をしっかり行うことが大切です。
特に投資初心者には、長期的な視点での積立投資をおすすめします。積立投資を行うことで平均購入単価を下げ、損失リスクを軽減することができます。 
よく比較されるアクティブ投資とは?

アクティブ投資(アクティブファンド)とは、ベンチマークする指数を上回るパフォーマンスを目指す投資方法です。アクティブ投資とインデックス投資は異なる特徴を持ち、よく比較されます。
どちらが良いか悪いかではなく、自分に合った方法を選択することが大切です。
アクティブファンドの特徴やメリット・デメリットについて見ていきましょう。
アクティブファンドとは?
アクティブファンドとは、ベンチマークを上回る成果を目指す投資信託のことです。
投資のプロが企業訪問や財務分析などを行い、成長性が期待できる投資先を選定します。また、市場の状況に応じて運用する銘柄や比率を柔軟に調整します。
インデックス投資に比べて人的コストがかかるため、手数料が高くなる傾向がありますが、指数を上回る値動きによって大きなリターンを得られる可能性もあります。
商品数が多く、投資対象は株式、債券、不動産、コモディティなど幅広いです。
一般的に、アクティブファンドはインデックスファンドよりリターンとリスクが大きくなるため、運用時には特にリスク管理に注意が必要です。
アクティブファンドのメリット・デメリット
アクティブファンドの主なメリットは、以下のとおりです。
・市場平均よりも大きなリターンを得られる
・指数に縛られない柔軟な運用が可能
・種類が豊富で目的に応じた商品を選べる
・市場全体が下落しているときでも利益を得る可能性がある
アクティブファンドは、日経平均株価やNYダウ、S&P500といった指数を上回る運用成果を目指すため、市場平均よりも大きなリターンが狙えます。
指数に連動しないため柔軟な運用が可能で、特定の業種やテーマ(AI、SDGsなど)に特化した商品も多く、目的に合ったファンドを見つけやすいです。また、市場全体が下がっているときでも利益を得られる可能性があります。
一方で、アクティブのデメリットは以下のとおりです。
・コストが高い
・必ずしも市場平均を上回るとは限らない
・ファンドマネージャー(運用会社)によって成果に差が出る
アクティブファンドは、商品選定や運用に手間がかかるため、インデックスファンドに比べてコストが高い傾向があります。信託報酬が1%〜2%を超えることも珍しくありません。
さらに、アクティブファンドが必ずしも市場平均を上回るとは限りません。市場平均を下回り、インデックスファンドよりパフォーマンスが劣る場合もあります。
アクティブファンドはファンドマネージャー(運用会社)の実力に大きく依存するため、実績や直近のパフォーマンスを十分に確認して選ぶことが大切です。
まとめ
インデックス投資は、初心者にもわかりやすく手軽に分散投資ができるため、多くの人に支持されている運用方法です。初めての資産運用にもぴったりで、積立投資とも相性が良く、NISAを活用すれば非課税で運用できます。
インデックス投資に興味がある方は、この機会に少額から始めてみましょう。また、自分に合った資産運用の方法が知りたい、専門家に資産運用の相談やNISAの相談がしたい方は、IFAへの相談も検討してみましょう。